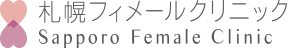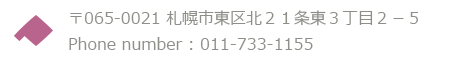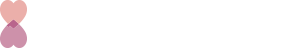インフルエンザのこと

昨日のbrilliant days F では、インフルエンザについてお話しました。
11月から3月ころまでは、インフルエンザの流行期です。
四季のある地域では、インフルエンザの流行は冬ですが、四季がはっきりしない地域では年中インフルエンザ感染が起こるそうです。
インフルエンザウイルスは、寒くて乾燥していると活発になりやすいのですが、なぜ冬に流行するかは、正確にはわかっていません。
はなやのどの粘膜が乾燥しやすくなること、寒さのため人がたくさん集まる場所で換気をしなくなることも要因とされています。
ヒトが感染するインフルエンザウイルスには、A、B、C、の3型がありますが、C型はかるい風邪症状で、6歳以下の子供にみられるもので、流行性のインフルエンザではありません。
B型はヒトのみに感染しますが、A型はヒト以外にもブタ、ウマ、ニワトリなどに感染します。
ヒトに流行するインフルエンザの7割ほどがA型です。
インフルエンザウイルスは、少しずつ変化をし続けているため、それを予想して、ワクチンも毎年少しずつ変えて生産されています。
インフルエンザウイルスの流行すると、H何N何とウィルス株を表現しているのをご存じでしょうか。
A型インフルエンザウイルスはヘマグルチニン(H)とノイラミニダーゼ(N)という、表面にある2つのたんぱく質の組み合わせで株を表現します。
2009~2010年に流行したブタインフルエンザはH1N1株の一つでした。
もっとも良い予防策は、ワクチン接種ですが、予防接種を受けたのに罹ってしまった、という話を聞いたことがあるのではないでしょうか。
予防接種をうけても、感染を完全に防ぐことはできないのです。ただし、罹っても重症化を防ぐことにつながります。
咳や熱、関節痛などが主な症状のインフルエンザ感染症ですが、ときに重症化してしまい、命を落とす人も少なくありません。
脳症やライ症候群などのリスクもあります。
インフルエンザワクチンは、生後6か月を過ぎていれば、たとえ妊娠中であっても受けることができる、安全が確認されたワクチンです。
インフルエンザにかかったら、休養がもっとも大切です。
治療薬もあります。
内服薬のタミフル、吸入薬のリレンザ、点滴で投与するラピアクタ、長期吸入薬のイナビルがあり、これらはすべて先ほどお話した、ウィルスの表面にあるたんぱく質であるノイラミニダーゼを阻害する薬です。
インフルエンザウイルスはヒトの細胞内に入り込んで増殖し、細胞外に出るときにノイラミニダーゼという酵素が必要になるのですが、この働きを抑えることにより、ヒトの体内でのウィルスの増殖・拡散を防ぐことができるのです。
また、インフルエンザに罹った人の、いわゆる濃厚接触者で、高齢者(65歳以上)、慢性の肺の病気がある人、糖尿病や腎臓病のひとには、症状がなくても予防投与をうけることができます。
毎年毎年、必ず流行するインフルエンザですが、今年はコロナウイルス感染との区別がつけにくくなるだろうということで、熱が出たときにどの医療機関を受診すればよいのか、今から不安に思っている方もいることでしょう。
発熱の症状の方を受け入れる体制を整えた医療機関を受診しましょう。
蛇足ですが、インフルエンザという名前は、まだウィルスの存在がわからなかった時代に流行したときに「天体の影響」と呼ばれたことに由来しているそうですよ。
Akiko